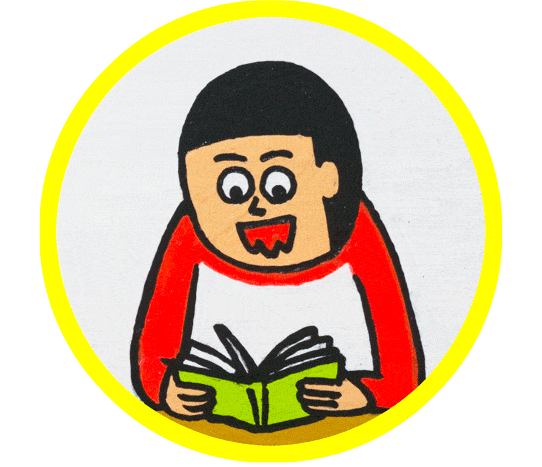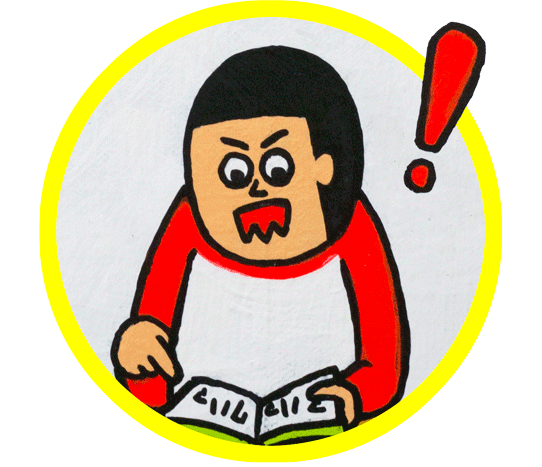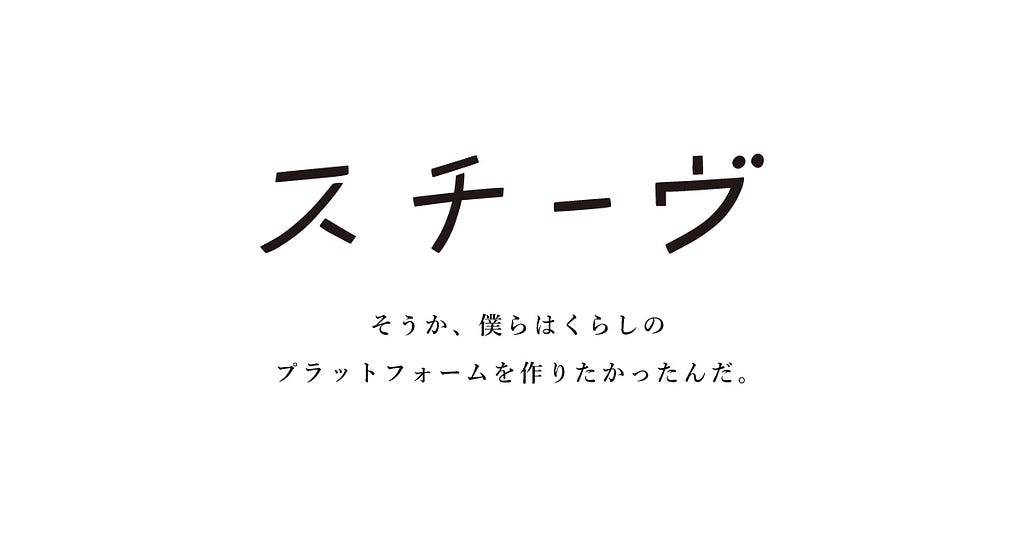
昨日、『灯台もと暮らし』というウェブメディアを運営する株式会社Waseiの代表・鳥井弘文(@hirofumi21)さんにお誘いいただき、「スチーヴ」のイベントに参加してきました。
スチーヴとは、『くらしのきほん』『灯台もと暮らし』『箱庭』の3つのメディア(現時点で)が集まってできたプラットフォームの総称です。
今回のイベントは「スチーヴの勉強会」という名目で行われました。
スチーヴがどんな思いで作られ、これまでにどのような準備をし、そしてどんな未来を描いているのかという内容と、松浦弥太郎さんが『暮しの手帖』の編集長時代から現在の『くらしのきほん』で得た様々な学びや気付きをお話していただきました。
すごいですね、ここまででまだ300文字ちょっとした書いていないのですがすでに5つの媒体名が出てきています。こんなことはなかなか珍しい。
そう、それくらい、ちょっとずつ毛色の違ういろんな媒体を集めて、「プラットフォーム」にしようとしているんですね。スチーヴは。
で、「スチーヴ」って?
話を戻します。
で、正直ぼくはこのイベントが始まるまで「スチーヴ」について全くピンときてなかったんですね。4月の第一弾のイベントに参加できていないというのもありますが、「暮らしのプラットフォーム」と言われてもなんだかあまりよくわからなかったんです。
それでも、昨日序盤で鳥井さんの説明を聞くと、「あぁ、そういうことがしたいのか」と合点がいきました。
2014年〜2015年あたりで大小いろんなウェブメディアが勃興し、そのどれがもが互いに競いあい、勝ったり負けたり、ときには蹴落としたり…、みたいなことがありました。
ちょっとしたブームのようなものだったのだと思いますが、それについて「もっと助け合って、みんなで盛り上がっていく方法ってないのかな?」と疑問に抱いていたとき、ひとつの方法として「スチーヴ」みたいなやり方があるんじゃないかと、そう至ったそうなのです。
「あぁ、たしかに」と。
お話を聞いていて、個人的には「助け(合う)」というのがひとつのキーワードになっているんじゃないかと読み取りました。
それを踏まえて、今後のビジョンまで語られていたので「そこまで描けているんだな」と思うと、すごくワクワクしました。
聞きながらふと、日本版スチーヴがある程度形になったとき、次は「アメリカはどうなんだろう?」「フランスは?」「メキシコは?」みたいに、ヨコに展開してもおもしろそうだなと思ったんですよね。
そんなことを考えさせてくれるくらい、今後が楽しみなメディア、いやプラットフォームです。
「そもそも、自分が書いた文章なんて誰も読んではくれない」
鳥井さんのスチーヴの解説のあとは、松浦弥太郎さんのお話。
正直、ここでは書ききれないくらい、熱量のこもった、さまざまな学びを与えていただきました。LINEの自分のみのグループにメモを取りながら聞いていたのですが、1時間ずっとスワイプする指が止まらなかったですね。
そんな松浦さんのお話のなかで、もっとも強烈に響いた内容のなかに「そもそも、雑誌でもウェブメディアでも、自分が書いた文章なんてユーザーは読んでくれない」というお話がありました。
普通、情熱を持って長い間雑誌やウェブメディアを作っていると「きっとこれはみんなに読んでもらえるだろう」と、読んでもらえる前提の思考になっていくと思うんですよ。実際、『暮しの手帖』はすごく売れてるわけですしね。
にも関わらず、松浦さんは「文章なんてそんなに読んでもらえない。ただ『見て』もらえるだけ。」とおっしゃいます。
実際に、いま松浦さんが運営されている「くらしのきほん」ではそのことを再優先に考慮したUI/UX設計にしているとのこと。
この、どこまでも客観的で冷静な視点がスゴいなと…。この発想はなかなかできることではないと思います。
たしかに、こんなに優れたコンテンツに溢れている時代です。「スルーされるのが前提」くらいのスタンスでいることが、結果的にユーザーにとってもいいコンテンツをつくるうえでの秘訣なのだと再確認しました。
最後に、イベントに協賛してくださった「Soup Stock Tokyo」のお粥もめちゃくちゃ美味しかったです。お粥って、あんなに美味しくなり得るんですね。
今年上旬の非礼をお詫びしたいと思います。
「スチーヴ」は今冬のリニューアルオープンに向けて準備中とのこと。楽しみに待っています。
【追伸】
「スチーヴ」の発音は「スティーブ」と同じイントネーションで大丈夫そうです。
text by @shimotsu_